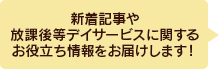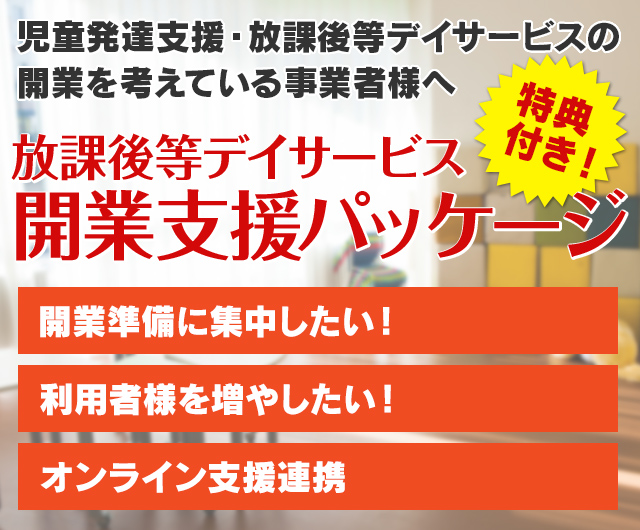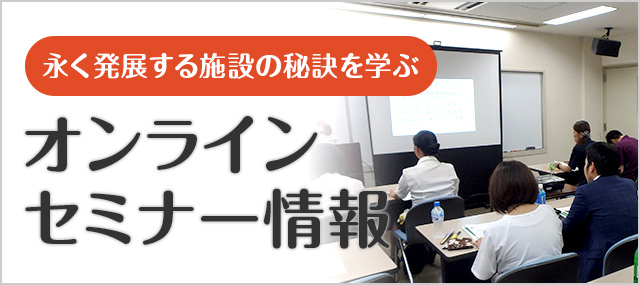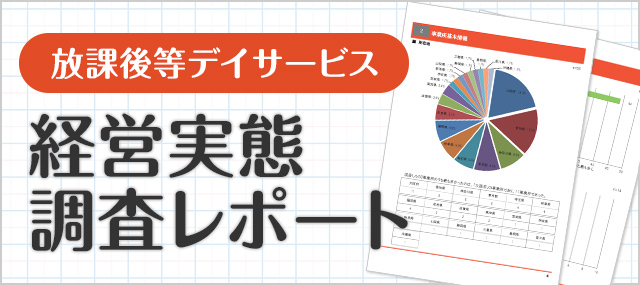放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
2025/03/25
放課後等デイサービス事例インタビュー

茨城県古河市で放課後等デイサービス 「くもとそら」や不登校や高学年の児童対応「くもとそらatネーブル」を運営する株式会社ソノママ様にお話を伺いました。
放課後等デイサービス『くもとそら』を立ち上げた経緯など、代表の鯉沼様からお話を聞くことができました。
他の放デイを選択できる環境を提供するために開所
インタビュアー(以下:イ)鯉沼様のお立場や施設での関わり方など簡単に自己紹介をお願いします。
鯉沼様(以下:鯉沼)株式会社ソノママの代表の鯉沼です。児童発達支援管理責任者としても勤務しています。
イ)開所されたきっかけを教えてください。
鯉沼)僕が違和感を覚えた療育方法への挑戦といった感じです。
と言っても、今ある療育方法がダメだからというわけではなく、主流と言われる療育方法に合わないお子さんは事業所選びが大変だと感じていたことに対してのことです。
私は、小集団の集団療育を主としつつ、幼稚園児から中・高校生まで通える多機能型の事業所に勤務したことがあります。
支援の形として高校生に合わせることは難しく、現場では幼稚園児でも分かるような形や、小学生に合わせる取り組みをすることが多くありました。
異年齢の交流としてはものすごく良いところもありましたが、一方で支援として考えた時に「これが高校生の支援として適切なのか?」「小さい子の成長に今必要なのか?」など難しさを感じた経験があります。
そもそも「どちらかの年齢に合わせるというやり方以前に、考えなくてはならないものがあるのではないか…」と思うようにもなりました。
そんな中で「あなたは、そのままで良いんだよ」という想いを伝えられる場所を作りたくて、開所へ踏み出しました。
放課後等デイサービスは、基本的に学校へお迎えに行き、帰所後は学校の宿題などをして、事業所ごとのプログラム、集団活動としての公園遊びやレクリエーションをしたりしますよね。
個々に合わせた課題に取り組む個別療育もあると思いますが、その時間軸のほとんどは事業所の時間軸に合わせたものです。
開所にあたり、その時間軸で目の前の子に必要な支援がきちんと届けられているのか僕の中では課題として残りました。
イ)1人1人に合わせた療育や想いを届けたいけど、年齢の大きく異なる集団では難しいと、もどかしさがあったのですね。
鯉沼)5年前の2021年に事業所を立ち上げましたが、そのころは放課後等デイサービスが急増した時期で、集団療育が一般的でした。
集団療育は必要なことです。ただ「その子にあった選択肢があるか」や「支援の幅(年齢による難しさ)は適切か」など課題は尽きることはなく、他の事業所が悪いということでもありません。
その場所が合わない子たちに対して支援をしたい。「あなたは、そのままで良いんだよ」という想い・願いのある事業所があることが、他の放課後等デイサービスも選択できることに繋がるのではないかと思いました。
10才までの感覚統合が子どもの成長に大きく繋がる

イ)開所の準備で大変だったことはありますか?
鯉沼)とても大変だったことを思い出しました。
事業所を開所する時に「小学校1年生から3年生までが対象です。」「地域の学校の子しか入れません」と言い切ったことによる関係者からの困惑です。
運営だけを見ればビジネスであり、且つ福祉であるために間口を広げておくべきです。それなのに自分で自分の首を絞めるような発言に「小学校3年生になったら、どこに行けばいいの」「支援学校の子を何で受け入れてくれないの」などの声を多くいただきました。
しかし最初にお話したように、必要な人に届けたいという想いから、敢えて小学1年生から3年生と区切り、地域の小学校限定にしていました。
高校生や中学生に必要なこと、小学生に必要なことは違います。小学3年生で区切ったのは、僕の中で10歳未満という1つの区切りがあるからです。
精神的な発達と体の成長という部分で分けて考えると、体の成長の方を先に整えてあげる必要があります。
療育では「感覚統合」(注1)と言いますが、五感に加え基礎的な筋力と体力を付けながら必要な支援をしていくと、出来ることも増えていきます。
その時期に伸び伸びと自分らしくいられることが、その子の今後の成長に大きく繋がるという確信があったので、あえて区切りました。
実は、今では4年生以上のお子さまにもご利用いただいていますし、支援学校の子もいます。
今度は受け入れを拡大したことに対して理解してもらえないこともありました。
イ)なかなか理解が得られなかった方々と今は歩み寄れたのでしょうか?
鯉沼)そうですね。めちゃめちゃ歩み寄れました。
僕が最初に小学3年生までと限定したのは、月並みですが本気で子どもの成長を考えていたからです。単なるビジネスとして事業を始めたわけではありません。
必要な人に届けたいという想いから、受け入れを変えただけで理念は変わっていません。
「そのままで良いんだよ」というメッセージは、スタッフにも理念として浸透させてきました。
スタッフを始め、行政や保護者の皆さんともすべてを話して付き合ってきたので、最初は理解できない、歩み寄れないという方もいらっしゃいましたが、今は歩み寄って仲良くさせていただいています。
話し合っても理解し合えない方もいます。それはどちらかが悪いというわけではなく、そんな時こそ他の事業所をおすすめできるいい機会だと思っています。
店舗も増えましたが、事業を拡大しようとしてきたわけではなく、利用してくださる方々の声、町の困りごとに対応していたら増えていったというだけの話です。
皆さんと相談しながら、事業しながら歩み寄れたと思っています。
(注1)感覚統合とは、日常生活で感じるさまざまな刺激や感覚情報を処理し、統合する能力のこと。人は五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を通じて外界からの刺激を感じ取り、脳内でそれらの情報を統合して、意味を理解しています。感覚統合がスムーズに行われていることで、身の回りの状況把握や自身の行動および他の人とのコミュニケーションなども円滑におこなうことができます。
放デイが開所できない物件を借りても諦めずに

イ)2021年に開所して、現在多くの施設を運営されていらっしゃいますが大変だったことはありますか?
鯉沼)施設を増やすことで大変だったことは2つしかなくて、その1つは資金ですね。どのようにお金を回して運営していくかです。
基本は融資なので、融資のタイミングと僕たちがやりたいことに対するスピード感と上手く合わないこともあります。
中長期的な計画の中、事業計画として施設を増やしたわけじゃなく、町の困りごとがあって、誰もやっていないけど誰かがやらなくちゃいけないから「僕がやります。」といった感じで進んできました。だから資金的にはいつも大変でした。
もう1つ大変だったことは、物件に関する知識の無さで苦労しました。
物件を借りるときには不動産会社が仲介に入ります。福祉側の人間は、“騙す人はいない”と根本で思っているのですが、放課後等デイサービスをやれると聞いていたのに、実際には出来なかった物件が2件ありました。それも契約して話が進んだ最終段階でのちゃぶ台返しでした。
しかしそれも経験として、どうしようかと考えた結果、この町にはなかったフリースクールのような「不登校の子の居場所」にすることにしました。
結局、居場所ではなく休憩所となりましたが、諦めなかったことで、放課後等デイサービスとしては使えない物件も、不登校の子のために活用できることになり、現在多くの方が利用してくれています。
ワンピースのようなチームに

イ)職員採用や職員教育でご苦労はありましたか?
鯉沼)スタッフの確保やスタッフの質の問題など大変とよく聞きますが、お陰様で株式会社ソノママではほとんど苦労することなくここまできました。
絶対上手くいくという保証はないのですが、僕の中で1つのやり方を見つけています。
ワンピースという漫画をご存じですか?ワンピースの主人公は、自分は「海賊王になる」と夢を語り、他のクルーもそれぞれ別の夢があります。
みんな夢が違うのに同じチームとして、めちゃくちゃ強く機能している理由は何なんだろうと考え、仮定でもいいからと、そのやり方を会社としてやってみたんです。
採用面接で、僕の夢として「そのままでいられる社会を作りたいんだ」と話をして、「あなたの夢は何ですか?」と質問します。その方の夢が僕たちの会社で叶えられそうであれば、採用させていただきます。
例えば、「学校を作りたい」「公園を作りたい」「保育園を作りたい」「宇宙に行きたい」とそれぞれいろんな夢がありますが、僕たちの会社で一緒に出来そうだと思える夢なら採用することを繰り返してきたら、皆が夢を話してくれるようになりました。
「私、保育園を作りたいんだよね」と語ったスタッフは、今では移動保育園をキャラバンのような形で具体化していこうと考えているようです。
スタッフがそれぞれの場所で夢を語っていると、「どうやらこの会社は楽しそうだ」と、見えない力みたいなものに人が集まってくれるようになりました。
だから本当に人には困ったことがなくて、古河市内の事業に関して求人は、ほぼ出していないですね。
イ)すごいですね。夢を言葉にするということは、前向きな気持ちになれるんですね。
鯉沼)そうです。組織として考えた時、ワンピースにマニュアルは存在しません。それぞれが考えて行動します。
本来、それぞれが考えて行動出来る会社が強いはずです。組織になるとマニュアルや、組織のビジョンやミッションに当てはめて、合わせられていってしまう。
それこそ、今までの療育方法でも感じた違和感である “合わせられていく” ということが、多くの会社の中でも起きているのだと思いました。
くどいようですが、マニュアルやビジョンがある会社がダメということではなく、世の主流な会社像から外れる勇気が持てるかどうかということだと思います。
今、みんながそれぞれ考えて行動してくれているので、僕1人で考えるよりも面白い方向に事業所が進んでいると思います。
職員と1対1でコミュニケーション
イ)職員様とコミュニケーションを取られるときに意識されていることはありますか?
鯉沼)3つあるなと思っています。
なるべく1対1で話すことに時間を取りたいと思っています。あとは皆で話す時間を作ること。最後はすべてを話すということです。
ごめんなさい。1つしゃべらないことがありました。それは給与で、それぞれ違う給与で働いているので、それ以外は何でも話すようにしていますね。
手前味噌ですが、僕が事業所に遊びに行くと本当に喜んで迎えてくれるスタッフたちにいつも助けられています。
今、何が欲しいかとスタッフに尋ねると、「僕と話す時間が欲しい」と言ってくれることがとても有難くて、ネガティブなことでもポジティブなことでも、自分がやりたいと思うことを僕と話したいと思ってくれる関係性が嬉しいです。こんなチームなので、強いし面白いです。

HUGは記録を取ったら、それが請求データに直結する
イ)HUGを導入しようと思ったきっかけなどはあったのでしょうか?
鯉沼)開所の準備をしているときに前職の同僚が別の事業所に移ったと聞いて遊びに行きました。
僕よりも発達障害の分野に知見がある方なので、良いシステムがないかと聞き、返ってきた答えが「HUG」でした。
もちろんその事業所でもHUGを使っていたので、何も疑うことなくHUGにしようと決めました。
イ)ありがとうございます。HUGを導入して良かったことなど何かありますか?
鯉沼)そうですね。大きく2ついいところがあって、1つはやっぱり連絡帳です。
オンラインで今日の様子を保護者に見せられることがめちゃめちゃ良かったです。
もう1つは、記録を取ったらそれが請求データに直結しているということが良かったと思いますね。
イ)業務日報にも写真付きで業務連絡されていたりなど機能を上手く利用されていますが、職員様と記録の残し方など相談されたのでしょうか?
鯉沼)僕は、「なるべく業務を減らそう」とずっと言っています。業務が増えないようにHUGを活用するようにとは話しました。
使い方としては、業務を減らすことを念頭に置いて、自分達が使いやすいように使ってもらう形を取っています。
分からないときは、すぐにサポートに電話
イ)施設が増えていく中で、連携も含めてHUGで使にくかったことなどはありますか?
鯉沼)使いづらさなどは感じていないです。実務レベルの請求のとき、どうしたらいいのかとすぐにサポートに電話をしてしまうので、本当に申し訳ないと思いながらも、すごく有難いと思っています。
あとは私自身が業務の中で、面倒くさいとか大変だと思う部分をHUGがカバーしてくれたら、もっと嬉しいなと思います。
イ)例えば、どんなところですか?
鯉沼)変更届などですね。行政に関する書類はスタッフに教えることが必要で、出来るスタッフがいたとしても最終的に代表である僕が見る必要があります。
その行政との書類のやり取りが一番面倒です。HUGで言えばボタンを押せば加算が付くけど、この書類関係は実際に行政で認証してもらわなければならない過程があるので、そこが紐づいてくれたらすごく助かります。
事業者側としては、めちゃめちゃ運営が楽になるんじゃないかと思いますね。
イ)弊社のサポートもご活用いただいているということですね。イレギュラーな対応の部分で、弊社でもお役に立てることが無いか今後検討させていただきます。
「ふるさと」のような存在に
イ)開所の準備に2年を費やされましたが、何が大変だったのでしょうか?今後のビジョンや事業展開をお聞かせください。
鯉沼)2025年5月の立ち上げ予定を含めると事業所は、放課後等デイサービスが6つ、児童発達支援が1つになります。そうすると毎日60〜70人の子どもたちが来る場所になります。
僕たちがやっていることは子どもたちの未来に繋がります。僕たちが歳を取ったころに活躍してくれる人たちを育てているので、それは「まちづくり」と言っても過言ではありません。
学校、先生、教育委員会、不登校の子どもたち、それぞれの関係性は「発達障害」という1つのキーワードで紐づいて、今の現状ではそれが絡まっているように感じます。
例えば不登校の理由が、先生が嫌だからとか、勉強が出来ないからと不登校になってしまう子どもが多いんです。しかし、先生側と話すと「発達障害だから特性上仕方ない」と言われてしまうことがあります。
集団を指導する学校という仕組みの中で、個別に手が必要となる子どもたちにかける時間を作り出すことは難しいのかもしれません。
これは先生が悪いわけでもなく、間違っても子どもたちのせいでもありません。
まちづくりという観点で見ていくと、これは学校だけの課題ではありません。
放課後等デイサービスから会社運営を始めましたが、僕は今、まちづくりをする別の会社にも参画させていただいています。
今後はその会社と共に「まちづくり」を地域の人達や行政と展開していきたいと思うし、最終的に「ふるさとづくり」として展開できればと願っています。
おかしな話ですが、「ふるさと」と言ってパッと思いつくのは、僕の場合はマクドナルドなんです。
実は高校3年間働いたバイト先でもあり、実家に向かう道の途中にマクドナルドが見えると、なんとなく「ふるさとに着いた」みたいな感じになります。
山や町並みもふるさとですが、どうやら ”それぞれの思い出” からくる「場所のふるさと」「心のふるさと」みたいなものもあるようです。
事業所「くもとそら」に通う子どもたちは、長いと小学校と同じ年月を利用してくれます。そんな子どもたちにとって、事業所を見た時に帰ってきたと思えるような「ふるさと」になりたいですね。
「心のふるさと」という意味では、今の時代でよく聞くSNS絡みのトラブルや見えない非行から、自ら戻ってくることができる子でいて欲しいという願いがあります。
自分のしていることに対して、「先生が危ないと言っていたな」「やめた方がいいかな」と感じた時にパッと先生の顔が目に浮かぶ。
何かに巻き込まれそうになった時、その子を引き止めて現実に連れて帰ってこられるような「心のふるさと」のような存在になりたいです。
おこがましいのですが、子どもたちの芯の部分をつくるため、療育をしない事業所として愛を届けられたらいいなぁと思っています。
イ)ありがとうございます。安心でき、信頼できる居場所作りですね。
本日はお忙しい中、貴重なお時間を頂きまして、本当にありがとうございました。
さいごに
弊社が提供している「HUG」は放課後等デイサービス運営会社が開発したソフトウェアです。
請求業務はもちろん、個別支援計画やサービス提供記録の作成から管理も簡単に行えます。
実際にHUGをご利用いただいている放課後等デイサービス事業者様の感想をご紹介していますので、請求ソフトや管理システムの導入を検討されている方はご参考くださいませ。
HUG導入のお客様の声はこちら
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】
-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
-
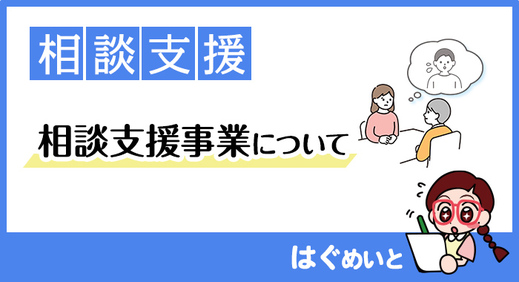
相談支援事業所について
-
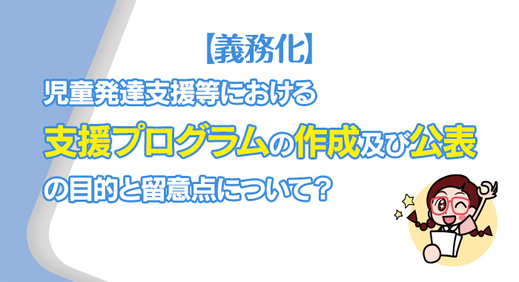
【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について
-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】
-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】
-

地域のお困りごとを解決するために事業展開
-

会社も利用者も地域に根付いていく【株式会社ネオハル様】
-

事業所と保護者の想いを繋ぐ相談支援専門員
-

「子どもを人間として見る」学問の視点に立った療育【一般社団法人かりなぽーと様】
-