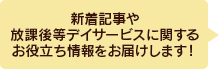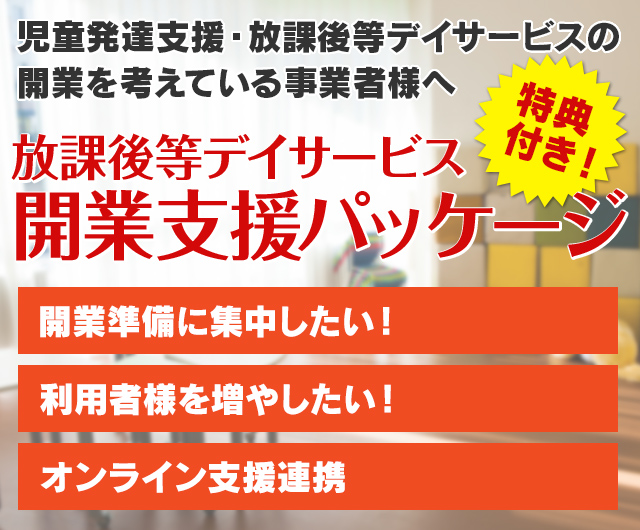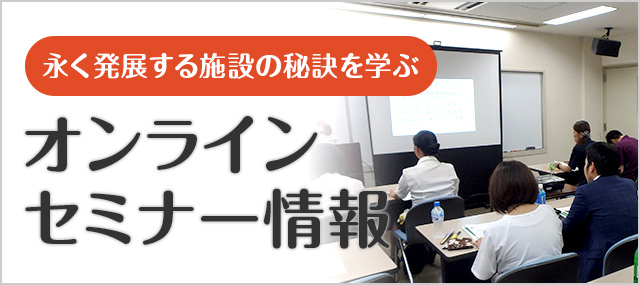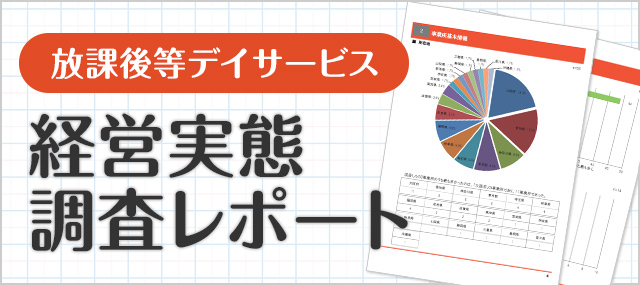放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
会社も利用者も地域に根付いていく【株式会社ネオハル様】
2025/02/12
放課後等デイサービス事例インタビュー

千葉県柏市で児童発達支援を運営する株式会社ネオハル様にお話を伺いました。
株式会社ネオハル様は『児童発達支援 根っこ』を、千葉県柏市で2施設を運営されています。
施設を立ち上げた経緯など、管理者の高江洲様からお話を聞くことができました。
保育士仲間が集まり児童発達支援を立ち上げ
インタビュアー(以下:イ)高江洲様のお立場や現場などの役割をお聞かせください。
高江洲様(以下:高江洲)夫と2人で「児童発達支援 根っこ」を立ち上げました。株式会社ネオハルは、夫が代表取締役をしています。
2つ目の教室をオープンしたので、私は2つの教室の統括管理責任者という立場で、療育の現場にも出ています。
イ)開所のタイミングからHUGを導入いただきましてありがとうございました。
まずは開所のきっかけなど経緯を教えてください。
高江洲)私も夫も違う放課後等デイサービスに勤務して働いていたので、いつか自分たちで理想とする施設を立ち上げたいという話をしていました。
私も夫も保育の専門学校を卒業しているので、保育士の友人が多くいます。その中で、施設を立ち上げたら手伝うと言ってくれるメンバーが揃ってきたので、タイミングを見て開所しました。
小さい子が大人になるまで、その子ども達に寄り添いたいという想いがあり、まずは児童発達支援を立ち上げました。いずれは放課後等デイサービスや就労支援、生活介護と繋げていきたいと思っています。
イ)ご友人が参加してくれたので最初から職員さんが揃っていたのですね
高江洲)立ち上げから手伝ってくれた仲間と一緒にホームページを作ったり、SNSで発信したりしながらさらに仲間を増やしました。
イ)開所時の採用が一番大変とも聞く中で、既にお仲間が集まっていたなら安心でしたね。
高江洲)最初はそうですね。一緒に働く仲間と教室の開所準備ができました。
それこそシステムを決めるときもみんなでネットで調べたり、HUGや他システムの方たちの話を一緒に聞いてもらい、意見を聞いて、使いやすそうだとHUGに決めさせてもらいました。
イ)ありがとうございます。2教室目も開所(2024年12月)されて順調に教室数を増やされていらっしゃいますが、開所で大変だったことはありますか?
高江洲)1つ目の教室は、オープンしてから2か月くらい利用者さんがいませんでした。
オープンしてから営業活動を始めたので初日は利用者さんがいない状態です。利用者さんがいなくて経営的には大変でしたが、ゆっくり時間をかけて納得できるまで準備することができ、利用者さんを1人ずつ増やしていくことができました。
オープンから8か月後には、定員を満たすことができ、さらには有難いことに待機してくださる方が増えてきたので2教室目をオープンすることになりました。
2教室目の初日は建物の中も完璧ではなかった中でオープンを迎えることになりましたが、待機していた方が2教室目に来てくださったので、オープン初日から利用者さんがいる状況でした。
1教室目で運営やHUGの操作に慣れていたこともあり、出欠であったり連絡帳など業務上でやらなければならないことに対して、初日にしてはすごくスムーズにこなすことができたと思います。
今の保護者はSNSをしっかり見ていいる
イ)1教室目は最初から利用者様がいなかったということですが、どのような営業活動で乗り越えられたのですか?
高江洲)児童発達支援なので、まずは相談支援事業所に挨拶に行き、市内の保育園にも全て挨拶に行きました。
未就学児のお子さんがいる保護者にパンフレットが渡るようにと、例えばパン屋さんやスーパーなど子育て世帯が多く行く場所にパンフレットを配りにいきました。
その後はSNSが強いですね。
インスタグラム経由で利用者さんが来るとは思ってなかったんです。あくまでも利用していただいている保護者の方への情報発信としてインスタグラムを始めました。
今はインスタグラムを見て見学に来てくれたり、スタッフとして求人に応募してくれたり、今の人はSNSをかなり活用しているんだと実感しました。
イ)SNSの投稿の仕方や投稿内容は、皆様でお話しされて更新されているのですか?
高江洲)そうですね。どんな記事が良いかなど話し合いました。
HUGの連絡帳に1日3〜4枚写真を添付しているので、写真を撮る習慣があります。写真係みたいなポジションの人がどんどん撮り、SNSにUPしている感じです。
普通に写真を投稿するときもありますが、リールを作ったり、ショート動画を作ったりして投稿を工夫しています。X(Twitter)など他のSNSも使い、常に情報発信しています。
イ)開所時だけでなく、継続して発信することで職員様の採用や利用者様の獲得に繋がったのですね。
最初の2か月間は利用者様がいらっしゃらなかったということですが、集まってきたと手応えを感じられたのはいつ頃ですか?
高江洲)最初の2か月は0人で、このまま潰れるのかと心配しましたが、1人ひとりと増えてきて8か月目くらいに定員100%になったと思います。それこそHUGの売り上げ実績記録を見れば分かりますが、秋には手いっぱいになって待機が出た感じです。
利用者さんが増えると、その方が口コミを書いたり、お知り合いに声を掛けてくださったようです。多くは保育園に子どもが通っているので、保護者のネットワークからのアナログな口コミです。
親御さんからの実際の口コミは、かなり重要なんだと改めて思いました。SNSは、投稿したら一気に情報共有できることがいいところですが、やっぱり両方大切ですね。
イ)口コミを聞いた方も、恐らく検索してSNSも見るから、ツールが揃っていることで、より利用者様に届いたわけですね。
HUGでコミュニケーションのきっかけを作る

イ)想いや活動の様子を写真でたくさん載せた可愛いホームページも拝見させて頂きました。
高江洲)福祉のイメージは、あまり派手ではなく、SNSなども積極的にはやらないものだと私は勝手にイメージしていましたが、保護者の方の目に留まるようにとの思いでやっています。
子ども達の支援もしながらで、時間が無い中で発信しているので大変ですが、スマホがあればどこでも発信できます。それこそHUGで記録するとか、連絡帳などへの記録も全部どこでも出来ますよね。パソコンでもタブレットでもスマホでも出来るし、その延長線上でSNSも発信しています。
イ)HUGの連絡帳や活動記などに写真を多く活用されていらっしゃいますね。
高江洲)HUGの連絡帳は、保護者の方から好評です。
今日やったことなどを上手く親御さんに伝えられない小さなお子さんが多いです。活動の様子を送迎のタイミングだけで全てを伝えきれる訳でもないです。でも活動時のお子さんの表情を見られることで親御さんは安心します。
写真をお子さんと一緒に見てくださる方もいるので、「活動の様子をご家庭での会話に利用してくださいね」とお伝えしています。
親御さんが、「この写真の時はどうだった?」「これ楽しそうだね」と話しかけることで、ご家庭でコミュニケーションが生まれるきっかけになっています。
保護者の方も携帯でHUGを見られるので、子どもを寝かしつけた後や寝る前に見るのが楽しみだと言ってくださる方もいます。
ちょっとしたスキマ時間でも見られますし、家族との情報共有が、違う場所にいてもできることがすごくいいと言っていただきました。
前の事業所の連絡帳は紙とペンだったので、やっぱり場所も時間も限られていましたが、良い意味でコピーとかペーストができるのはシステムのいいところですね。
だからHUGも使いやすいですね。紙の連絡帳の味もありますけどね。
イ)お子様たちの素敵な表情があっての写真です。日々の療育内容がとても充実しているからですね。
育ちのベースを作る集団療育
イ)教室では、どのような療育を中心に活動されているのでしょうか?
高江洲)まず集団療育か個別養育かに大きく分かれるところだと思います。私たちは、みんなで楽しく過ごせる居場所を作りたかったので、メインは集団療育にしました。
集団でも、お勉強や体操などメインの療育はいろいろあると思いますが、子どもたちが大きくなるまでに必ず獲得しておかなければならないことは、自分のことは自分でできるようになることです。
それが育ちのベースになるからです。基本的なことですが、靴下を自分で履くというところなどから生活に密着した支援を療育のベースにしています。
お友達と喧嘩したら「悲しいよね」と伝えることはもちろんですけど、実際に喧嘩も体験することが子ども達にとって必要なことなので、とにかくみんなでたくさん遊ぶことにしています。
その中でお友達に伝えたいことを、どうやって伝えたらいいのか、コミュニケーションを促す活動が重要だと思います。
大人になっても、「お友達と一緒に遊ぶと楽しい」という気持ちを持っていて欲しいので、遊びの中からいろいろなことを身につけていけるように、いろいろなイベントを実施しています。
例えば、動物園に行けばもちろん楽しいことですが、その為には決められたことを守らなければなりません。うちは帽子とビブスを被って行くので、帽子とビブスを被る。靴を履く。順番に乗車する。車の中ではチャイルドシートやジュニアシートを付けるなど、動物園に着くまでにいろいろなルールを守らなければなりません。
しかし、ルールを守ることで楽しい思いができることを知り、「先生の話はきちんと聞こう」という気づきに繋がるように支援しています。
動物園に行っても、順番を待たなきゃいけない場面や、本当はライオンをずっと見ていたかったのに、集団で動いているから移動しなきゃいけないときの気持ちの切り替えなど、家族で動物園に行って、自分の好きなものだけを見られるときとわけが違います。
お友達がウサギを見たがっているから、一緒にウサギを見たら可愛かった。帰りにお友達とウサギのことをおしゃべりできて楽しかったなど、家庭とは違う体験になります。それが子どもたちの経験になるし、心の根っこが育つ取り組みだと思っています。
毎週のイベントごとにスタッフ会議で何度も体制確認

イ)野外活動は職員の方が大変だと思いますが、内容などは相談されているのでしょうか?
高江洲)週のイベント時はスタッフ全員が登山のようにリュックを背負っています。出掛けることはリスクが高くなるので、それだけ準備が大変ですが、スタッフを増やすなど毎回体制も含めて準備しています。
月に1回の会議はもちろん、週末ごとに会議をして翌週のお出掛けについて確認もするし、前日は工程表を組んで、担当を組みます。
担当は子どもの担当制にすることもあるし、場所によっては場所に担当者を配置します。遊具の滑り台担当、ブランコ担当というようにして、子どもが自主的に遊べるけど、目が行き届くようにします。
「〇〇ちゃんがブランコからすべり台に戻ります。」という具合にスタッフ同士で声を掛け合い、チームワークで見守っている感じですね。
大きな公園に行って事故にならないように、とにかくスタッフ全員でコミュニケーションを取りながら対応しています。
イ)児童発達支援は年齢層が低いので特に目が離せないですよね。
高江洲)1歳から6歳までのお子さまをお預かりしているので、思い切り走れる子もいれば、ようやく歩き始めたという子もいます。
目的に行くまでの歩行スピードも全然違いますが、そこは大きい子達に、小さい子が頑張って歩いてるから「ちょっと待ってあげよう」と声をかけることで、小さい子を思いやる気持ちが芽生えますし、逆に小さい子達はどんどん進んで歩くお兄ちゃんお姉ちゃんの背中を追って必死に付いて行きます。
施設ではあるけど、長時間お預かりしている中で、友達であり兄弟であるような関係性が見られます。
「お手伝いしてあげたい」と自発的に行動して、「楽しいね」という思いを共有することが出来ていることをすごく嬉しく感じています。
イ)集団療育だからこそですね。
離職者ゼロだから次の準備ができる
イ)2教室目は開所されたばかりですが、2つの教室で関わりはありますか?
高江洲)教室同士は車で20~30分くらいの比較的近い位置にあり、同じ市内です。もともといたスタッフが数人異動していますので、合同でお出掛けもします。
最寄りの大きな公園は同じなので、遠足の目的地を同じにして、子どもたちは公園で一緒にご飯を食べたりします。
先日は茨城県にある小動物の動物園に行きましたが、現地で集合しました。そのときしか会えないお友達とお互い抱き合う場面もあり、すごく可愛いかったです。
人数が多くなれば、大人の負担は正直それだけ大きくなるんです。でも子ども達は、それだけでテンションが上がるし、屋外なのでさらにテンションが上がる状況です。教室を問わずスタッフ同士も連携を取らないといけないので大変ではありますが、スタッフたちも楽しむことをモットーにしていて、対応しています。
本当にスタッフも大変だと思うんですが、子どもたちと一緒に戻ってきて「楽しかったね」「次は、どこに行く」と子どもと話している姿を見て、良いメンバーに恵まれたと本当に感謝しています。
イ)職員の方が楽しく働いている職場は、お子さんも楽しく通われている印象があります。そこが運営が上手くいく秘訣なんですね。2教室目で新しく採用もされましたか?
高江洲)採用しました。すぐ決まりましたし、来年度の新卒採用も内定者が4名います。
イ)たくさんの新卒採用ですね。
高江洲)春を目標に3つ目の教室の開所を目指して、物件を探しているところです。
イ)では、これからまた忙しくなりますね。
高江洲)そうですね。スタッフの離職率が低くて、離職者ゼロなんです。
産休や育休に入っていた方たちも4月には戻ってくるので、そのタイミングで3教室目を準備しています。
イ)育休明けても戻ってくる場所があるというのは安心ですね。
高江洲)子育て世代のスタッフが多いです。みんな日々忙しいです。
日々の子どもたちの記録が終わらないとスタッフは残業が多くなると思うんですが、だからこそ毎日きちんとやることができていれば、慌てることもなくなります。
そういうところで、HUGへの入力はすべての記録に繋がるのでかなり助かっています。

HUGはみんなで一斉に入力できる。そこが一番の魅力
イ)初めての開所時にHUGをご検討いただいたきっかけはありますか?
高江洲)基本的にSNSを使って調べました。
ネットで児童発達支援の運営システムなどを調べると概ね3つくらい名前が出てくるので、その名前をX(Twitter)に入れて評判を調べました。
最初は、値段がネックでした。利用者がいない節約が大事な時期です。システムを入れないことが一番の節約ではありましたが、そこは私が代表にシステムを入れたいと頼みました。
後から入れることもできますが、最初からシステム化したいという想いが私にはありました。
イ)色々調べられた中からHUGに決めた決め手は何になりますか?
高江洲)決め手はSNSです。利用している施設の方の感想など口コミからの評判です。
画面も見やすかったし、今回の「はぐめいとのインタビュー記事」も参考にさせて頂きました。使いたい機能が揃っていたのと、説明書も見やすいし、キャラクターもあって可愛い感じですよね。
正直、どのシステムでも大きく変わるわけじゃないと思っていたところ、送迎のチェックが付けられることと、請求と連絡帳が同じシステムということが有難かったです。
連絡帳はこのアプリだけど、請求はこのシステムと、別々のシステムを使用している事業所が多いと周りの福祉職員や経営者に聞いていたんです。
それが全部1つになっていたら使いやすいのでは!と思いました。複数のシステムを入れると現場の混乱に繋がるのではという懸念がありました。
スタッフは、送迎が終わって事務所に帰ってきたら、やることがいっぱいあります。
例えば、遠足に行くと一日の記録などは戻ってきてからになります。遠足が終わって、送迎から事務所に戻ってきてからです。
今は「私は日報書きますね」「私は連絡帳を更新していくね」と携帯で連絡帳をどんどん公開するスタッフもいれば、横でパソコンから日報を書くスタッフもいるし、シフトを作るスタッフもいて、事務書類を全てHUGで、みんなで一斉に入力できる。そこが一番の魅力に感じています。
連絡帳に写真を入れられるのもいいなと思いました。保護者の立場で考えると、自分の子どもの写真が送られてきたら嬉しいですよね。
療育の手間は惜しまない分、事務的な時間は削減したい
イ)施設数が増えるとお手頃に使って頂けるので費用感も抑えられると思います。
高江洲)そうですね。運営の話になりますが、今は2つの事業所の売上を比較したり、パソコン上で2つの教室が見られるし、事業所間の連携も取りやすいですね。
イ)2つの教室を統括されるお立場だと、両施設の情報確認が必要ですね。
高江洲)そうなんです。指示書と呼んでいますが、1日の工程表も擦り合わせがしやすいし、合同イベント準備では電話で話しながら、お互いにHUGで同じ画面をリアルタイムで見て、利用者の人数を見ながら相談できるのも助かってます。
イ)ご活用頂いて、弊社としてもとても嬉しいです。
高江洲)HUGがないと全然回らないです。
イ)ありがとうございます。あったら嬉しい機能など要望はございますか?
高江洲)HUGはすぐに「反映」できる機能がありますよね。例えば今日の利用者一括編集で「反映」ボタンは、すごく楽なんです。1人1人時間をぽちぽちと打たなくていいので。そういう機能がもっと増えたら嬉しいです。
とにかく子ども達の支援は、手をかければかけるほど育ちに繋がるので手を惜しみませんが、運営管理の事務的なことは時間をかけずに楽に誰でも出来るっていうことが重要なので、HUGさんには、「こんな機能はないですか?」とよく連絡しています。
イ)承知しました。これからもご質問・ご要望の連絡をお待ちしています。
地域に根差した会社として「ゆりかごから墓場まで」
イ)最後の質問になります。今後のビジョンを教えてください。
高江洲)株式会社ネオハルは、地域に「根を張る」、地域に根差した会社です。利用者さんにも地域に根差して欲しいという想いと、1歳で出会った子の成長をずっと見守り続けたいという気持ちがあります。
子どもが大きくなっていくと利用できる施設が少なくなっていく現状の中、自宅から遠い生活介護や入所施設を利用しなければならないと聞いています。
私たちの教室は千葉県柏市にありますが、児童発達支援から放課後等デイサービスを利用して、その後は就労支援やグループホームといった具合に、この地域で利用者さんがずっと過ごせるような枠組みを作りたいと思っています。
利用者さんとその家族を「ゆりかごから墓場まで」ずっと支えていけるようなそんな会社にしたいと思っています。
イ)見通しがつくと保護者様も安心して子どもを通わせられますし、信頼感が増しますね。弊社にも就労支援施設があり、見学ツアーなども開催しています。よろしければご覧ください。
高江洲)心強いです。今日のインタビューも、最近日々の業務に追われていたので、初心に返ることができて楽しかったです。
イ)こちらこそ楽しかったです。本日は、貴重なお時間を頂きまして、本当にありがとうございました。
さいごに
弊社が提供している「HUG」は放課後等デイサービス運営会社が開発したソフトウェアです。
請求業務はもちろん、個別支援計画やサービス提供記録の作成から管理も簡単に行えます。
実際にHUGをご利用いただいている放課後等デイサービス事業者様の感想をご紹介していますので、請求ソフトや管理システムの導入を検討されている方はご参考くださいませ。
HUG導入のお客様の声はこちら
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
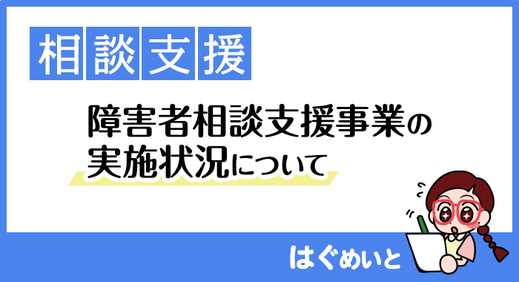
障害者相談支援事業の実施状況について
-
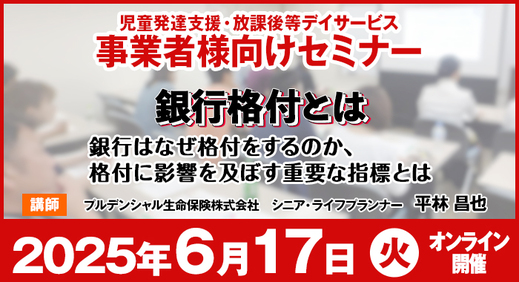
銀行格付とは 〜銀行はなぜ格付をするのか、格付に影響を及ぼす重要な指標とは〜
-
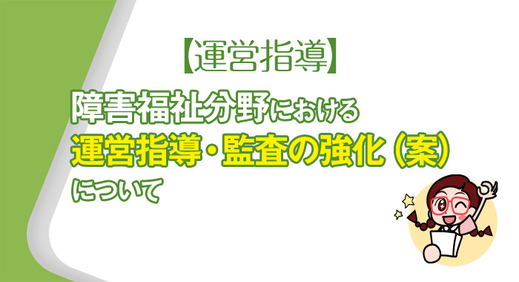
【運営指導】障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について
-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】
-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
-
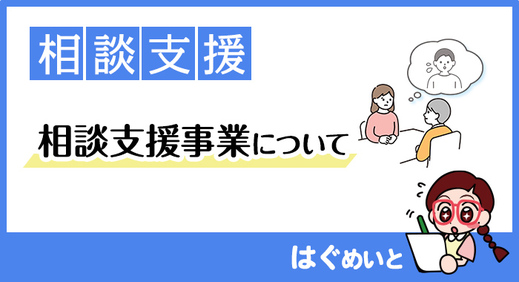
相談支援事業所について
-
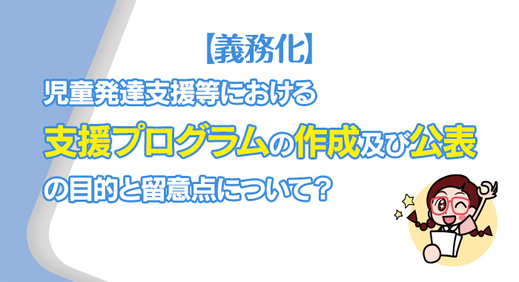
【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について
-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】
-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】
-

地域のお困りごとを解決するために事業展開
-