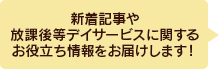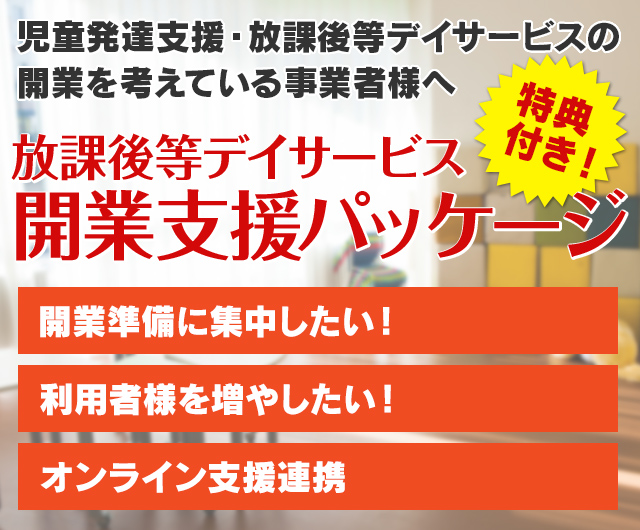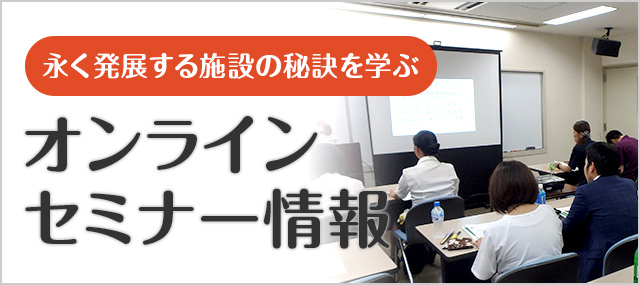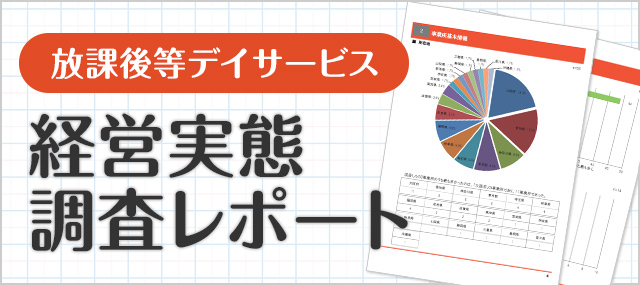放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
事業所と保護者の想いを繋ぐ相談支援専門員
2025/02/04
相談支援事例インタビュー

愛知県知多郡東浦町で児童発達支援センターを運営する社会福祉法人 太陽様にお話を伺いました。
社会福祉法人 太陽様は、2023年5月1日に『児童発達支援センター はるかぜ』を設立されました。
児童発達支援センターは、児童発達支援の療育に加えて保育所等訪問支援と障がい児相談支援を兼ね備えた地域の中核施設です。
施設を立ち上げた経緯など、センター長の横尾様と相談支援専門員様から相談支援事業についてお話を聞くことができました。
地域の要請に応えて児童発達支援センターを設立
インタビュアー(以下:イ)相談支援事業所を始められたきっかけを教えてください。
横尾様(以下:横尾)東浦町で児童発達支援事業を立ち上げようとした際、町からの要請もあり児童発達支援センターという立ち位置で開所することになったので、児童発達支援事業に相談支援事業と保育所等訪問支援事業をセットで運営することになったからです。
イ)なぜセンターでの運営を要請されたのですか?
横尾)この施設の目の前には、石浜住宅という県営の大きな団地があります。
ここはもともと昔ながらの5階建ての団地で、愛知県は団地を壊して建て替えるにあたってPFI事業(注1)を活用する計画が上がりました。
5階建てを10階建てにして生まれる空き地に、民間機関を活用しながら公共サービスを提供する事業計画の公募があり、事業計画を発案した建設会社から、実際に福祉事業を展開する社会福祉法人として一緒に事業に参画しないかとお誘いをいただきました。
当初の計画では、空き地に保育園と児童発達支援を運営するつもりで参画しましたが、東浦町の6か年計画の中の福祉計画の中には、児童発達支援センターを設立する計画があり、東浦町から「せっかくなら児童発達支援センターをやってくれないか」とお話しをいただきました。
東浦町としては、国が示した指針の中で「児童発達支援センターは各市町村に少なくとも1か所以上設置すること」と示されていたからです。
相談支援事業は初めてなので大変なことになることは重々承知のうえで、児童発達支援センターを立ち上げることにしました。
イ)法人として相談支援事業のご経験はなかったのですね。
横尾)そうです。初めてだったので相談支援の経験がある方を採用することにしました。
(注1)「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を目指します。

知らずに飛び込んだ相談支援専門員という仕事
イ)相談支援専門員様は、もともとどんなところで相談員をされていたのでしょうか?
相談支援専門員様(以下:相談支援専門員)最初は近隣の市の社会福祉協議会(基幹相談支援センター)、そのあとは多機能型事業所で障がい児相談支援の相談支援専門員をしていました。
横尾)相談支援専門員さんとは、太陽のグループ施設に通う子どもを通した知り合いでした。
相談支援専門員)当時は多くの子どもたちを担当していたので、太陽のグループ施設にもよく支援の一環で通っていました。
イ)なぜ相談支援専門員になられたのでしょうか?
相談支援専門員)もともとは保育士です。前職の保育施設では施設長をしていました。
自分が産休に入る前、“自分の子どもを保育園に預けて、保育士として他の人の子どもたちを預かる仕事” にいたたまれない気持ちになり、退職しました。
その後、求職するにあたって保育士の資格を活かそうと、保育士の資格をベースにした相談支援専門員という仕事を見つけて、どういう仕事なのか分からないまま、この世界に飛び込んでしまいました。
保育士として児童発達支援は理解していたつもりでしたが、この仕事に就くまで放課後等デイサービス(以降:放デイ)はもちろんのこと、就労支援B型などを含めた障がい者福祉全体の支援制度を全く知らなかったので、当時は本当に毎日が学びの日々でした。
相談支援専門員として入ってすぐに子ども35人の担当に。その翌週には大人が20数人加わるなど、60人ほど担当することになりました。
保育園時代の担任と違い、倍の人数でしたがやるしかない状況でした。
担当には出所者の大人の方も含まれていて…。保育士として子どもしか担当して来なかった私は、本当に不安しかありませんでした。
精神障害や発達障害の病名すら知らずに入ったので、大変なことばかりでしたが、同時に勉強になることも多くありました。
相談支援専門員は、とにかく相談者の話しを聞く
イ)限られた時間と情報の中で関わり方や支援方法など、どこから知見を深められたのですか?
相談支援専門員)毎月モニタリングとして会って、丁寧にお話しをする必要がある利用者さんがいました。
最初は、訪問しても暴言で追い返されたりもしましたが、訪問の回数を重ねるごとに会話を重ねることで距離は縮まっていきます。
そんな体験を多くしてきたことで、会話や支援の必要性を強く感じていきました。
当時の職場の社会福祉協議会には相談員が20名ほどいて、同期もいました。
職場環境は良かったので、相談員として皆さん多くの担当を抱えながらも、私の悩みや話しを聞いてくれてフォローしてくれました。
センター長もモニタリングに同行してくれたりして私は経験を重ねられたので、大変だと言われている相談支援のイメージは、そこまで悪くはなりませんでした。
イ)相談支援は大変だけど、仲間にフォローされて続けることができたわけですね。
どうやって担当の人と距離を縮めていくのですか?
相談支援専門員)とにかく話しを聞くことです。「ご飯食べた?」など、たわいのない話から話を聞いて、相手を気にかけていることを伝えていきます。
”話しにくいから” と相手から距離を置かれないようにしています。
イ)業務のモニタリングとして質問するのではなく、話かけていくのですね。
相談支援専門員)今でも昔の担当の人に道で偶然会ったら話しかけます。「元気だった?寒いね。」などたわいもないことですが、今も昔も変わらず相手から話を聞くことに徹しています。
聞くことはすごく難しいと感じているので、相手が「相談しようかな?」と話し始めてくれる瞬間を見逃さないように、振り返って話ができるように担当の情報を覚えるようにしていました。もちろん会話の中にある情報もあとで必ずメモしています。
イ)現在、はるかぜの障がい児相談支援は何人担当されていますか?
相談支援専門員)55人程です。今、東浦町の放デイを利用している担当の児童がいないので、町内の放デイ事業所は、ほとんど訪問したことがありません。障がい者福祉支援事業所もありません。
町内には受け皿が少なく、受け入れに余裕がないので他市町にお願いして、放デイを利用してもらっている状況です。
児童発達支援は、はるかぜを含めて受け入れが少し増えてきたのですが、放デイはまだ受け入れが少なく空きがなく、来年1年生の児童は町内で放デイを利用できる子が1人もいない状況です。

相談支援専門員の一日
イ)一日の仕事は、どのような流れになりますか?
相談支援専門員)モニタリングも含めてほとんどが訪問です。ご家庭もありますし、来年1年生になる親子と放デイの見学に同行することもあります。
また、通っている放デイに行き渋りがあり、別の放デイを提案する必要があると判断したときは、別の放デイの見学に同行するといったこともあります。保育園や学校は必要があればその都度対応します。
イ)事業所にはほとんどいないのですか?
相談支援専門員)日程調整は自分で行うので、事務所にいて集中的に書類を作成する日は作っています。
イ)一日多い日で何件回りますか?
相談支援専門員)一日4件ですね。訪問して1〜2時間はお話しますので。
担当する児童のお誕生日月が多い時期は仕事量が多くなりますし、秋からも忙しくなります。
12月中旬には新1年生の計画を提出するので、今は見学同行や計画書の作成予定がたくさんあります。
相談支援専門員は事業所と保護者との間に立って想いを繋げる
イ)相談支援専門員のやりがいはどんなところですか?
相談支援専門員)一番嬉しいのは、担当の相談者に「相談支援専門員さんに相談して良かった」と言ってもらえた時です。
「話したいことがあった」と言ってもらえたり、子どもが走り寄ってきてくれたときなど、見返りを求めるわけではありませんが、”一生懸命やってきた甲斐があった” と思える瞬間があるところです。
イ)相談支援は定期的な支援で、毎日ではないのでお子さんとの接点は少ないと思っていました。
相談支援専門員)事業所に通う保護者の方からお話しを聞くことは多くあります。事業所に直接言えないことなどは、了解を得たうえで調整して伝えるなど、保護者の方との連絡は、こまめにしています。
事業所と保護者の間に立たせていただいています。せっかく双方の意見を聞ける立場にいるので、想いのすれ違いは修正して、想いを繋げていけたらと思っています。
伝えるときも事業所の士気に影響しないよう気を付けています。
事業所の方がどう思われているか分かりませんが、こちらとしては「話しにくい人」と思われないように、些細なことでも情報共有するようにしています。
事業所にモニタリングで訪問したときには、保護者の方の喜びの様子などもお伝えしています。もちろん保護者の方も伝えていると思いますが、私が重ねて伝えるように心掛けています。

HUGは加算の登録がわかりやすい
イ)相談支援でもHUGをご利用いただいています。どのあたりが使いやすいですか?
相談支援専門員)何の加算を登録できるのか分かりやすいですね。最近は医療的ケア児の子が増えてきたので加算の取得も増えてきました。
支援の予定を入れておけて、支援したらボタンを押すだけで請求につながるところがいいですね。
イ)HUGに要望はありますか?
相談支援専門員)毎日入力する日報の記録の中で、こまかな経過記録を利用者で検索して情報を絞れたら嬉しいですね。
他の事業所から相談支援を引き継ぐとき、経過記録を出してもらうことがあります。利用者で絞る機能があると、経過記録として出力できます。
また、研修で事例を提出するときや利用者が移管するときなど経過記録をお伝えした方がいい場合などに利用できると思います。
イ)なるほど、分かりました。社内に持ち帰り検討させていただきます。
(2025年2月5日追記)
アップデートを行い相談支援事業HUGに業務日報の機能を実装いたしました。
その日に対応した利用者様や時間、内容を記載することで一日の業務内容が登録でき、対象期間で利用者様毎に出力できるので会議等にも活用いただけます。
相談支援専門員という仕事を知ってもらいたい
イ)最後に相談支援専門員としての今後の目標などをお聞かせください。
相談支援専門員)相談支援専門員の名前自体が浸透していなくて、仕事内容の理解や担当が付いている意味を分かってもらえないので、そこを分かってもらいたい気持ちが大きいです。
相談者や保護者と一緒に考えてあげられる立場であること、「何でも話してね」と声をかけていますが、遠慮や身構えて話してくれないことをなくしていきたいです。
そのためには相談支援専門員という仕事を知ってもらい、「気軽に相談できる人」そんな立ち位置の人になりたいです。
イ)大変勉強になりました。貴重なお話しをありがとうございました。
さいごに
弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。
また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。
相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
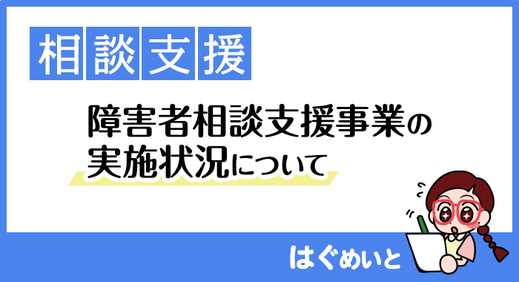
障害者相談支援事業の実施状況について
-
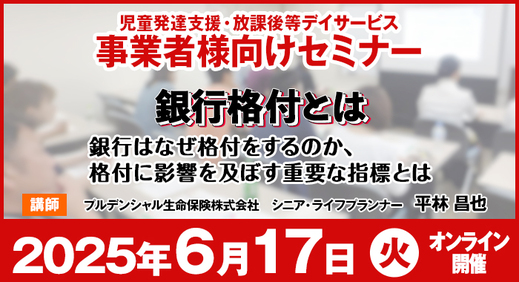
銀行格付とは 〜銀行はなぜ格付をするのか、格付に影響を及ぼす重要な指標とは〜
-
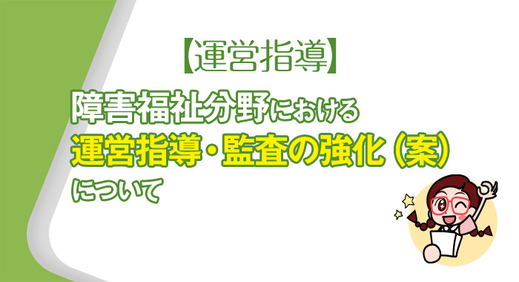
【運営指導】障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について
-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】
-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
-
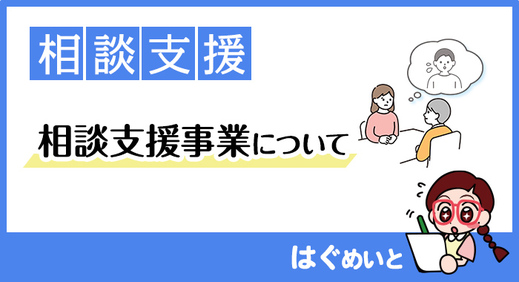
相談支援事業所について
-
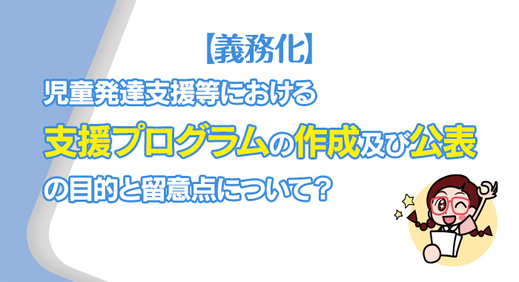
【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について
-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】
-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】
-

地域のお困りごとを解決するために事業展開
-