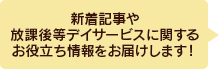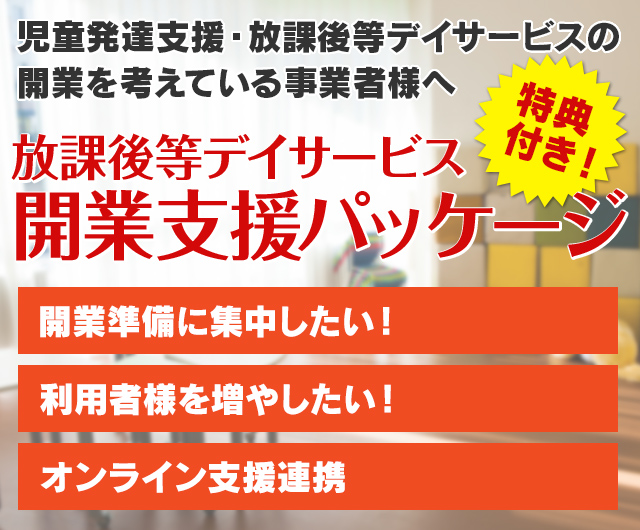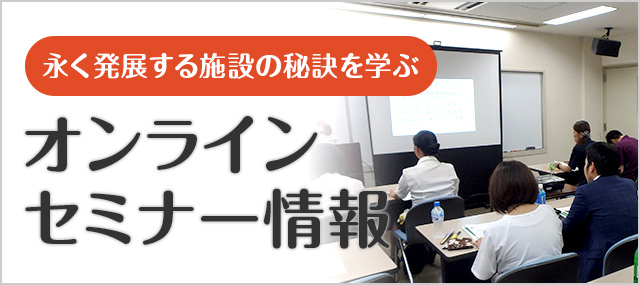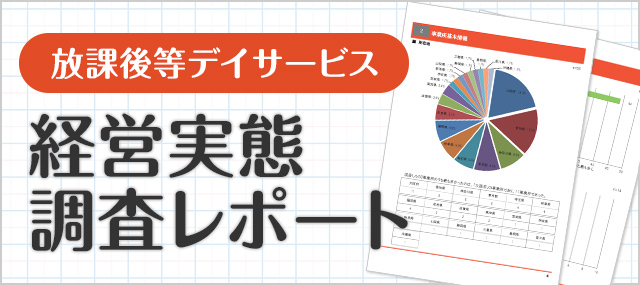放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
地域のお困りごとを解決するために事業展開
2025/02/12
相談支援事例インタビュー

大阪府池田市で相談支援センターを運営する株式会社ワンズトライン様にお話を伺いました。
株式会社ワンズトライン様が運営する『やわら相談支援センター』は、重症心身障がい児者のための相談支援事業所です。
やわらケアサポート、やわらリハビリ訪問看護ステーション、やわらソレイユ、やわら介護研修センター、やわら介護タクシーと多くの事業を展開していらっしゃいます。
相談支援センターを立ち上げた経緯など、代表取締役の岡本様からお話を聞くことができました。
医療的ケア児コーディネーターと呼ばれて
インタビュアー(以下:イ)簡単に自己紹介をお願いします。
岡本様(以下:岡本)株式会社ワイズトライン代表の岡本です。
大阪府池田市で要介護高齢者及び医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を対象とした、医療・介護・障がい福祉サービス事業を運営しています。
その中に、やわら相談支援センターがあり、僕は医療的ケア児コーディネーターと呼ばれてます。
イ)相談支援事業ではお子さんは何人ぐらい担当されていらっしゃいますか?
岡本)17人です。うちは重心専門の医療的ケア児専門の相談支援事業所です。だからそんなに多くはありません。
医療的ケア児は、放課後等デイサービスだけではなく、医療的な居宅介護も併用して使うので、両方支援が必要になります。放課後等デイサービスは障がい児支援になりますが、居宅介護は大人と同じ障害者支援のサービスになり、受給者証が2つ必要になります。
法律が違うので、行政によっては受給者証ごとに支援計画も2つの場所に提出することになります。
イ)ほとんどの医療的ケア児が居宅介護を使うのですか?
岡本)結構多いです。あとは短期入所もあります。レスパイトとしても使われます。それは障がい児福祉サービスだからです。
一般的な障がい児支援から見るとレアケースに思われるかもしれませんが、うちは医療的ケア児の子ばかりなので利用は多くなります。
また、障害福祉サービスと医療では制度が違うので、それを取りまとめる人がいないとまとまらないことから「医療的ケア児とその家族を支える法律」(注1)ができ、医療的ケア児コーディネーターという仕組みができました。
池田市で医療的コーディネーターの資格を持つのは、うちの訪問看護の看護師と僕です。うちは訪問看護事業もありますし、2025年4月から重心の放デイが池田市の中核事業所になることになりました。ですから半分行政として機能します。
これからは、池田市に転入してくる子の情報や病院から退院が決まった子の情報などが直接来るようになります。その場合、まずは訪問看護の方に病院から連絡が来るので、訪問看護の担当と僕が病院に出向くことになります。
病院のカンファレンス(注2)は、医療と福祉の3者で行い、長期的な計画を立てていくことが池田市の方針として決まっています。
イ)大阪はセルフプラン率が高いですか?
岡本)医療的ケア児のセルフプラン率は高いですね。
行政としても基本的にはセルフプランは望ましくないと考えているので、これから相談支援を増やしていこうと推奨しているので、これから増えてくると思います。
イ)市から相談対応の依頼が来ることはありますか?
岡本)相談窓口は決まってるので、医療的ケア児だったらそのままうちに来る感じです。
イ)池田市では、医療的ケア児は流れが決まっているのですね。
(注1)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
(注2)カンファレンス(conference)とは、「会議」などを意味し、医療や福祉の現場では、情報共有などの目的でカンファレンスが開催されます。
医師や看護師、介護士、患者や家族などが参加し、治療についての情報共有やケアプランについて話し合います。

訪問看護から重心の放課後等デイサービス事業に
イ)元々の事業は介護や訪問看護だったのですか
岡本)二十年ほど前に訪問看護事業から始まりました。
訪問看護の中には、小児の看護もあり、お母さんが買い物に行ったり、寝る時間が取れないなどの相談があり、最初は長時間訪問することで対応していました。
長時間訪問をして寝てもらったり、買い物に行ってもらう時間を作りましたが、それも限界があり、子どもの成長とともに「居場所を作って欲しい」と変化していきました。
地域には重心の放課後等デイサービスがなかったので、「うちがやりましょう」と引き受け、10年前に池田市で初めて重症心身障害児専門のデイサービスを作りました。
ですから、利用者さんの居場所を作っただけで利用者さんが変わったわけではありません。
訪問看護の利用者さんが医療的ケア児だったので、訪問して看護する代わりに施設で長時間預かります。そうすることで、お母さんは仕事に復帰できたり、お買い物とか休んだりすることができるようになりました。
イ)重心の放課後等デイサービスを始めることは、大変でしたか?
岡本)訪問看護をやっていたので、お母さんとの信頼関係の中で協力を得て作り上げていった感じですね。
当時は、「障がい児のデイサービスをやるけど、どんな施設がいいですか?」とヒアリングしながら作っていきました。
イ)職員の方は新規に雇用したのですか?
岡本)半分ぐらいはそうですが、訪問看護の看護師が家に行くか、施設に行くかだけの違いです。
今は兼務が少なくなりましたが、放課後等デイサービスの看護師が緊急の時に利用者の自宅に訪問することもありますし、訪問看護から施設へ支援に入ることもあります。
イ)保護者の方は、すごく安心できるシステムですね。
岡本)重心の放課後等デイサービスは、そもそもそういう仕組みになっています。
訪問看護や病院と併設するように作られています。だから、看護師全員が非常勤でいいんです。
イ)確かに人員配置基準が違いますね。
岡本)全員非常勤で良いというわけではありませんが、病院や訪問看護の合間に対応してもいいという意味です。
医療的ケア児は、病院から退院したら在宅の訪問看護で生活を落ち着かせて、第一段階として重心のうちに来ます。そして落ち着いたら他の放課後等デイサービスに振っていく流れです。
まずはここで慣れてもらい、対応の仕方がわかってきたら他の放課後等デイサービスを紹介します。僕が運転してツアーを組んでます。安定してきたので、そろそろ2か所目を探しませんか?と促しています。
重心の放デイから医療的ケア児の相談支援に
イ)それは中核施設だからですか?相談支援だからですか?
岡本)相談支援はどちらかというと池田市の要請を受けて始めた事業です。
相談支援をやるきっかけになったのは、重心の児童発達支援・放課後等デイサービス事業をやっているからですね。
イ)重心の事業所を始めて、訪問看護もやってるから医療的ケア児の相談もという流れですね。
相談支援事業所自体は、運営され始めて何年ですか
岡本)2年です。2年前まで医療的ケア児の相談支援事業所は”0”で、池田市では問題とされていました。
医療的ケア児のための相談支援員がいない。相談支援員はいるけれど、医療的ケア児の訪問看護がわからないから受けられませんという事業所がほとんどでした。それでセルフプラン率が高い状態でした。
福祉側からすると、医療側からはどちらかというと下に見られがちで、言いづらいこともありします。看護師さんに「来て」とは言いづらいらしいです。
イ)医療的ケア児に対応できる相談支援事業所がなかった背景から、池田市の要請もあり相談支援事業所を始められたわけですね。
相談支援員が担当者会議を開きますが、ここに集まるのですか?
岡本)うちの事業所に呼んで、みんなが集まります。
医療的ケア児は病院で手術などがあると、支援の仕方が変わります。また入学や学校が変わったら送迎の方法や通学支援を使うかなど、生活レベルがかなり変わるので、頻繁に招集して実際に集まります。オンラインはあんまり使ってないですね。
集まるのは、使っている放課後等デイサービス全部と相談支援専門員の私。訪問看護を行っている事業所と保健師さん、そしてご両親です。多い時は10人くらいになります。
相談支援専門員は調整役です。日程の調整とか大変ですけど、意外と集まります。
重心の事業所さんは皆さん熱心ですよ。児発管の都合が悪くても誰か代わりに来てくれます。命を扱っているので対応方法を間違えるわけにいきませんから熱の入り方が違います。
基本的に訪問看護をやってるところが居宅介護事業を一緒やっていたりするので、同じグループの人も多く、割と知った顔同士が集まります。
やっぱり地域の事業所なので連携が取りやすいですし、来れなかったとしても、直接行って話を聞いたり、議事録持って行ったりして話をすることができます。

担当者会議の一番の目的は事業所同士を連携させること
イ)担当者会議で主にお話をされるのは相談支援専門員の岡本さんですか?
岡本)MCみたいな感じです。話したい内容と計画書を作るために「これどうですか?」と聞いて、お互いの担当するところをまとめて話します。
担当者会議の一番の目的は、事業所同士を連携させることで、連絡先を交換させることが一番重要です。横で繋がって、直接やり取りしてくれた方が早いですよね。
基本的にうちが相談支援している子は、放課後等デイサービスを100%使っているので、事業所の方が横の繋がりを持っていることが多いです。
イ)調整連絡はどういう内容が多いですか?
岡本)容態とか処置の内容が変わったことなどです。
例えば、「水分の摂取量が少なくなってるから、これも気をつけてください」とか、「発作が起きたから、こういうことに気をつけてくださいね。」などです。
イ)命に関わる部分なので、繋がることはとても大事ですね。
岡本)相談支援が入ってよかったとよく言われます。
事業所同士お互い何をやっているかわかりません。別に連携を取りたくないわけじゃないけど、わざわざ行って聞いてもいいのかな?など遠慮している感じがあります。
そこを繋いであげることが一番の役割ですね。
イ)相談支援事業所は大阪府池田市ですが、対応範囲はどのあたりまでですか?
岡本)池田、箕輪、豊中の3市です。
イ)3市で書類の違いなどルールが違うことはありますか?
岡本)書類を出す先とかは、違ったりはします。アセスメントシートにサインが必要かなど細かい違いもあります。
アセスメントシートにサインをもらって管理をしていくことが本当に大事なことなのか?ありのままを行政に伝えていくことが大事なのではないか、と考えさせられることがあります。
アセスメントでよく聞くのは、困難事例などです。相談支援員側からすると、本当に伝えたいことが書けないことがあります。
例えば、本人にサインをもらう必要があるので、ゴミ屋敷だったからと言って「ゴミ屋敷」とは書けないんです。
行政としては、本当の情報が欲しいですよね。「ちょっと散らかし気味」か「ゴミ屋敷」と書くかではイメージが変わってくるんです。
伝えたいことを伝えられないままオブラートに包んで書いていいものなのかと。
実際の様子や支援計画を作るまでのやり取りした内容をメモして、別に提出したりはしますが、それも面倒だと議論に上がっています。
うちは困難事例がないので、HUGに直接ありのまま書いて提出しているので問題はないですけどね。
なければ社会資源を自ら作り、介護タクシーで通学支援
イ)岡本さんは、ずっと障害福祉関係に就いていたのですか?
岡本)違います。公務員を経て宅地建物取引士として不動産関係の仕事をしたり行政書士として遺言書作成や相続手続きの仕事をしていました。
この業界に入ってから言語聴覚士の国家資格を取得しました。
外国人の在留資格申請とかもするので、介護人材としてネパールからの介護人材支援をしたり、独居高齢者の支援をしたりとか、空き家問題に対応してきました。
基本的には地域のお困り事を解決する会社です。僕はどちらかというと行政のお困り事の解決に携わっています。
普通の児童発達支援や放課後等デイサービスは他にもあります。他になくて困っているから、うちがやる感じです。
イ)相談支援業務と重心の放課後等デイサービスもされている中で、大変な部分はどこですか?
岡本)特殊なので、社会資源を探すんじゃなくて、社会資源を作っていかなければならないというところです。
他の放課後等デイサービスにコンサルとまでは言わないですけど、重心施設を見学に来てもらって、やりたいという人を支援したり、利用者さんを紹介して情報を連携したりします。相談支援がそこまでやる必要があるかは知りませんが、無料でやっています。
医療的ケア児に対応しているのはこの地域では僕らぐらいしかいないので、やってくれる人がいたら連携を取って、事業が潰れないように助けていきたいです。
イ)すごい責任感と使命感ですね。
岡本)必要なのになかったら自分たちで作ります。通学支援がそうでした。
支援学校に入学する利用者さんの相談支援で、お母さんが仕事しているので学校に連れて行けない。でも呼吸器を装着しているから、通学バスには乗せられないと言われたそうです。
お母さんが連れて行くのは難しいということであれば、大阪府には医療的ケア児の通学支援の補助があり、通学に特化して介護タクシーと看護師代が出ます。
イ)医療的ケア児のことを考えるとバスよりタクシーですよね。
岡本)行政に詳しく聞いたら、添乗する看護師は、介護タクシーで子どもを送ったら、現地から公共交通機関で帰ってこなければいけないルールでした。
介護タクシーは現地までの助成だからです。ありえない話です。
白タクは使えないから介護タクシーが必要です。うちも最初から介護タクシーは持っていたわけではないので、みんなで二種免許を取得しにいきました。
それでできたのが『やわら介護タクシー』です。現実的に自社で作らないと無理なんです。
介護タクシーと放課後等デイサービスと訪問看護を持っている会社はそんなにないと思いますよ。
うちは独居高齢者の支援もしているので、介護タクシーで朝は通学支援、昼からは高齢者の通院支援をしてビジネスモデルとしてどんどん組んでいる感じです。
イ)足りないなら作らなければならないと、駆り立てられて社会資源を作ってきたわけですね。
岡本)継続性も必要なので、そこにビジネスとして空きがないように、従業員にもお給料を渡さないといけないので潰れないようにです。
イ)相談対応していると、どうしても足りない部分に気が付きますよね。
岡本)「社会資源が足りないね」って普通は相談支援が終わると思うけど、僕らは作り出してきました。
相談支援事業所は、利用者のみならず『地域を守る』
イ)ホームページを拝見しました。様々な事業がある理由が分かりました。
岡本)やりたかったわけじゃなくて、増えちゃった感じです。
儲かるかどうかは別で、とりあえずやってみて、それが継続できるような形になったら、周りに見本を見せて、真似してもらって地域に資源を作っていく。
だからまず作らないといけないのです。今、他に介護タクシーは3社ぐらい増えました。連携も取れていますから、台風や災害時の対応をみんなで統一するなど相談しています。
そうすると利用者さんも迷わないし、安心です。一方だけがサービスが悪いなど差を生まないようにするには連携は欠かせません。
相談支援事業所は、利用者のみならず『地域を守る』ことも必要なので、社会福祉協議会も自立支援協議会も委員として出席します。
これが相談支援の業務なのかはわかりません。相談支援をやっていると行政から重宝されますが、人件費は出ない手弁当です。
それでも経営者として、いち早く情報を得ることで必要な事業を作れるし、ビジネスになっていきます。
相談支援は、その子だけではなく、その子を地域と共にどうやって支えていくかにかかっています。いい地域を作っていかなければなりません。行政もそこを見ていると思います。
相談支援をやっていると、事業所の足りなさとか質とか肌感覚でわかるし、唯一遠慮なく事業の中身を見ることができます。だから相談支援は、放課後等デイサービスなどを経営している会社がやるべきだと思うんですよね。そして地域の課題を解決して欲しいです。
それに相談支援で直接の人件費を得るのはすごく大変なので、多く相談を受け付けて計画だけ作っていても実際に解決につながらないと正直きついと思います。
これからはITツールを使って、いかに簡素化して、相談件数を持ち、収入を確保していくかが重要になります。

保護者の方の生活リズムに合わられるデジタルサイン
イ)そうすると、HUGがお役に立てている部分はありますか?
岡本)僕が思うところ、デジタルサインが一番大きいですね。HUGを使わせていただいて、HUGから離れられない原因はデジタルサインです。
障害児相談支援に関して、デジタルサインはすごく使えます。
相談支援は、まずアセスメントです。お話を聞くためにご自宅を訪問します。話を聞きながら内容を記載し、「ここは、ちょっと違いますね」とか、軽微の修正などを児童本人やお母さんがどう思っているかなどをその場で継ぎ足していきます。
そのあとはオンライン上で内容を確認してもらいます。オンライン上でデジタルサインがもらえるので、修正の度に何回もお母さんに予定をしてもらって、お宅にお邪魔しなくて済みます。
イ)何度も往復しなくてもよくなるわけですね。
岡本)訪問して大事な部分を直接聞いて、書類のサインなどをオンライン上でできるようになりました。
以前は本人にアセスメントをして、お母さんから話を聞いて、内容を全部記載して埋めて、またアポ取って確認をもらうことを繰り返していました。本当に何回も訪問しないといけないんですよね。
でも、お母さんは忙しいし、何回も何回もお宅にお邪魔するのも申し訳なかった。お母さん方も確認がオンライン上で済むことを、「すごくありがたい」と言ってくれます。
イ)やはり保護者の方もお忙しい方が多いですよね。
岡本)家に来られるのは嫌ですよね。散らかっていたりとかもありますし。
イ)そうですよね。お子さんもいるし確かにそうです。
訪問先で内容をそのまま入力される感じですか?
岡本)訪問先の時もあります。ある程度準備しておいて、あとは端末を持参して、出向いた先でお母さんや本人の役割など、聞いたことをその場で入力していきます。
その場で終わったら、その場でサインしてもらって終わることができるし、その場でできなかったとしても、後でサインをもらうこともできるので、いろいろな状況に対応できています。
サインだけのために再訪問したり、郵送したりすると思うと、今となってはぞっとします。
”お母さんに時間を取らせない”ということが一番大きいです。それが多分一番ネックだと思いますね。
今回の法改正はお母さんの離職防止という目的もありますよね。共働きでお母さんが就労されている方が多いので、デジタルサインはそれにすごくマッチしています。
自分のペースで書類を確認できてサインできるので、「ここを直しました」と説明を入れて連絡しておけば、次の日の朝にはサインが返ってきています。
イ)保護者の方の生活リズムに合わせることができるんですね。
保護者の方でサインが難しいなどと言われたことはありますか?
岡本)今までデジタルサインができなかった方はいないです。
最初はペンなども用意していましたが、指でとても綺麗に書いてくれます。今時の方は慣れています。荷物の受け取りもデジタルサイン化が進んでいますよね。
これまで問題は一切なく、やりにくいと言われたこともないです。むしろ何回も行って日程調整したりしなくて済むので助かるので、すごい売りだと思います。
イ)他にお役に立てている機能はありますか?
岡本)他のシステムを使ったことがないので比較して言えないのですが、放課後等デイサービスの請求業務は僕がやってるから、放課後等デイサービス用のHUGに切り替えるだけなので助かっています。
重心の放デイは、今後5人定員の生活介護をやる流れに
岡本)HUGさんにお願いしたいことが一つあります。
2024年4月の法改正で、重心の放課後等デイサービスと生活介護の多機能が明確化されました。HUGは生活介護には使えませんよね。
多分、これから生活介護が増えると思います。僕の周りでも2、3か所が生活介護の多機能になっています。今回、うちも生活介護事業を申請したので、そこだけ別のシステムを使わないといけなくなるんです。
放課後等デイサービスと生活介護の多機能を一緒にする事業所は今後増えると思うので、一緒に使えるようにして欲しいです。
イ)生活介護の請求は、どんな感じになるのでしょうか?
岡本)18歳になったら児童福祉法から外れるので、重心の子は生活介護が必要になります。
今まで生活介護だけ別のジャンルでしたが、2024年の法改正で放課後等デイサービスの延長としての生活介護が認められて事業がやりやすくなったんです。
だから一緒だと思います。今の18歳の子が19歳になったら利用するからです。名前が変わっても人員配置も同じで、重心の生活介護の多機能になるだけです。
イ)これから重心の放課後等デイサービスは、5人定員の生活介護の多機能をやる流れが当たり前になってくるんですね。
岡本)そうなんです。医療の進歩で長生きできる方が多くなったので、学校を卒業したら生活介護が標準になります。多機能に限りますが、場所も変わらないし、スタッフも一緒で居場所は変わりません。
イ)5人定員の多機能型は、児童発達支援をしていても認められるのですか?
岡本)児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護で定員5名です。
利用者さんは変わらないので、同じ情報を引き継いでいけるように、同じ請求業務ができると助かります。少なくとも請求だけはできるようにお願いします。
イ)確かにそうですね。いただいたご意見を社内で共有させていただきます。
全く別の事業が一つのサービスとして共有
イ)最後に今後の予定など教えてください。
岡本)2025年4月に外国人としてネパール人の訪問介護が解禁されるので、訪問ヘルパーの授業と受け入れ施設を作っています。
イ)ワイズブレイン介護アカデミーと、ワイズブレイン人材紹介サービスですね。
岡本)ネパールのWHO認定健康都市であるドゥリケル市と連携し、日本の医療介護現場で働くネパール介護人材育成プロジェクトが始動します。
入国管理局の業務も僕自身が行政書士なので在留資格も僕が申請します。
イ)ネパールの方の支援とは具体的には?
岡本)現地に日本語学校を持っている関東の会社とご縁があり、その日本語学校と提携しました。
その生徒さんをうちで初任者研修を実施して地域に紹介したり、自社で活躍してもらいたいと思っています。
ネパールで勉強中の方が春には第一期生として来日します。その方たちの活躍の場をこれから作っていかなければなりません。
即戦力になるネパールの看護師さんに日本語を学んでもらい、日本で働いてもらうプロジェクトなので、池田市と業務連携して、地域課題にもより一層取り組んでいきます。
意外に思われるかもしれませんが、サービスで共通する部分があるので一個でやるよりも効率がよく、その結果で事業の幅が広がります。
介護タクシーにしても、ただ単に介護タクシーをやっているわけではなく、朝は介護タクシーで通学支援をして、午後から高齢者支援することで、全く別の事業が一つのサービスを共有できて無駄がなくなり、どの事業も盛り上がり続けてこられました。
イ)相談支援事業の取り組み以外でも多くの事業や想いをお伝えいただき、誠にありがとうございました。
さいごに
弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。
また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。
相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-
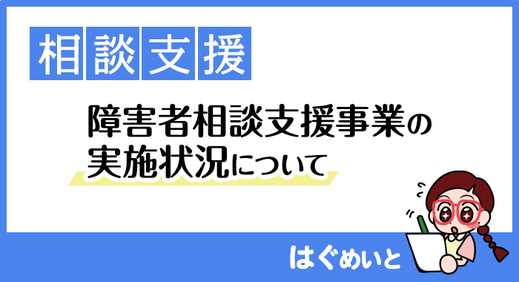
障害者相談支援事業の実施状況について
-
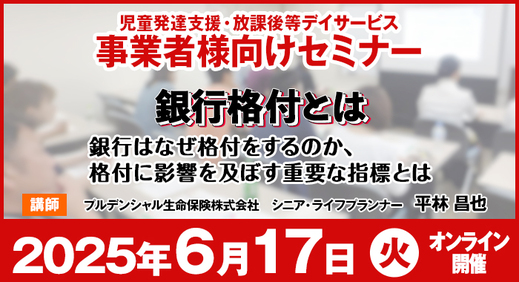
銀行格付とは 〜銀行はなぜ格付をするのか、格付に影響を及ぼす重要な指標とは〜
-
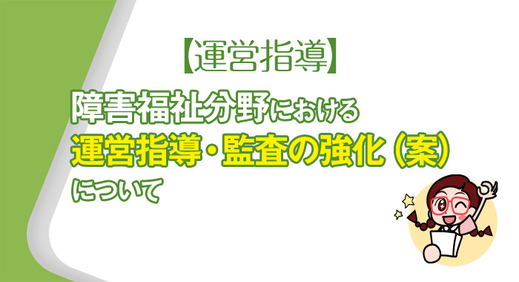
【運営指導】障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について
-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】
-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
-
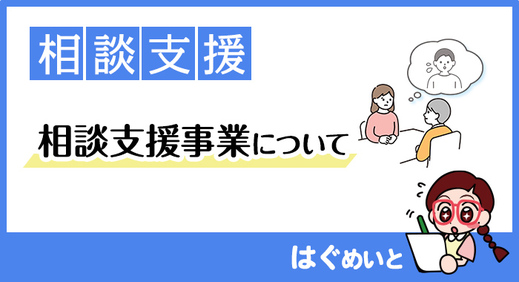
相談支援事業所について
-
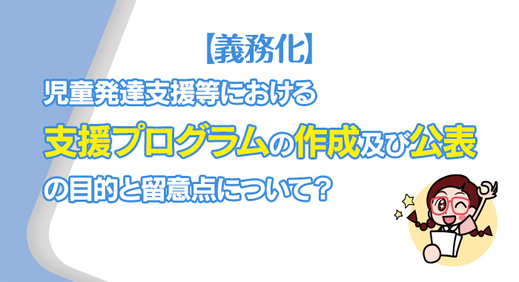
【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について
-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】
-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】
-

地域のお困りごとを解決するために事業展開
-