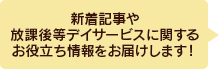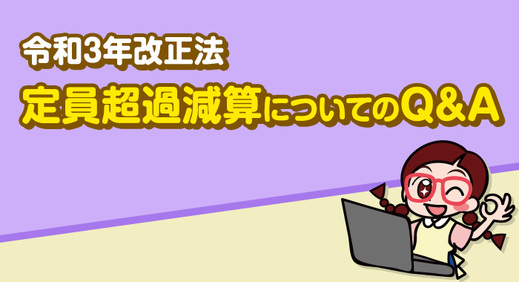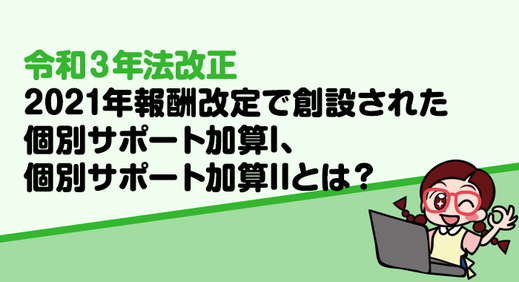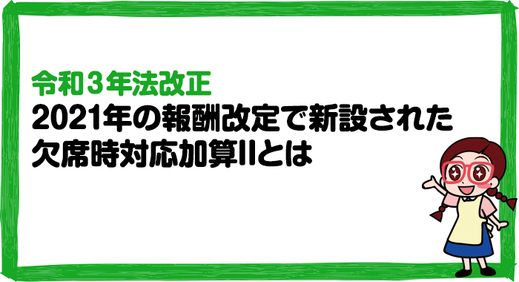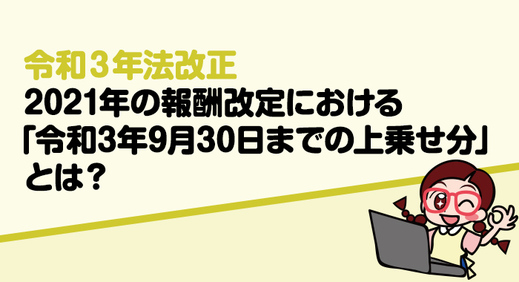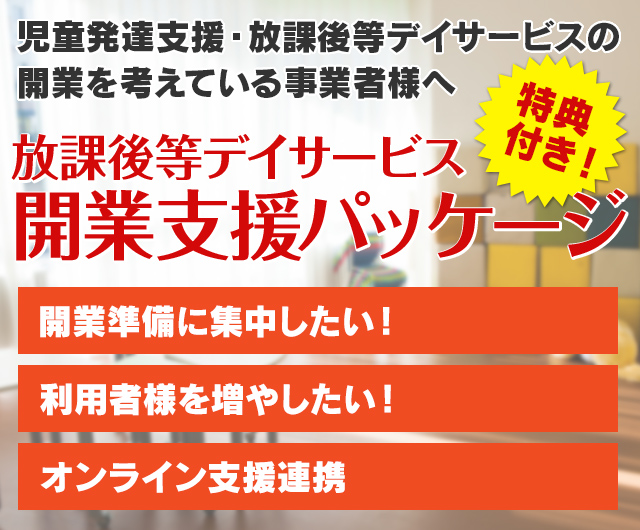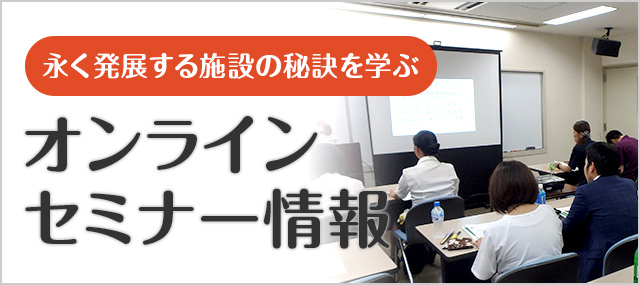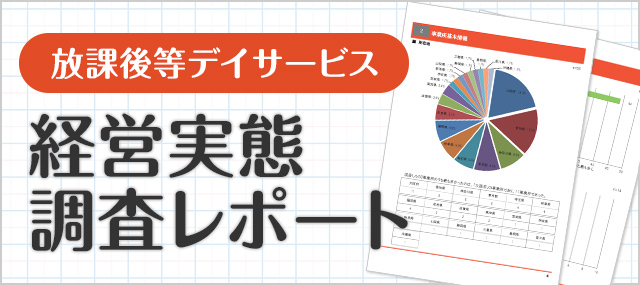放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
令和3年法改正以降の障害児通所支援のあり方とは?
2021/07/29
放課後等デイサービス 報酬改定2021
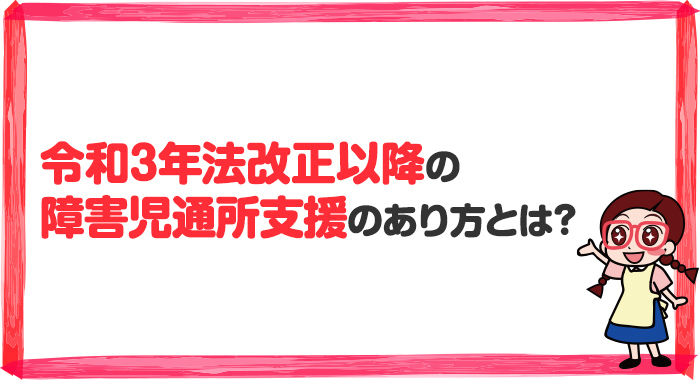
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】法改正以降の障害児通所支援のあり方に関する検討会』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
(1) 【令和3年法改正】2021年の報酬改定における事業所内相談支援加算に関わるQ&A
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における専門的支援加算に関わるQ&A
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定で創設された個別サポート加算I、個別サポート加算IIとは?
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点
障害児通所支援のあり方は変化していく
今回は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部から令和3年6月14日に公開された『第1回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」』を参考に、一部抜粋してご紹介します。
放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害福祉サービスにおいて、障害児通所支援の新しいあり方が検討されています。
これまでも、2012年(平成24年)にはバージョン1.0へと、そして2018年(平成30年)には児童指導員・保育士が必須となるバージョン2.0へと変化してきました。
さらに今回の法改正により、バージョン3.0の時代がいよいよやってきたのではないか、と個人的には感じています。
1、児童発達支援センターの位置づけについて
●センターに求められる「中核機能」について、法的に果たすべき機能が明確になっていない、一般の児童発達支援事業所との役割分担が明確になっていないという指摘について、どう考えるか?
●「福祉型」と「医療型」のセンターの在り方についてどう考えるか? …など
『児童発達支援センターの位置づけ』という点において中核機能は明確になっておらず、「そもそも法的に何をやらなくちゃいけない所なのか?」ということが指摘されています。
また、一般の児童発達支援センターとの役割分担が明確になっていないところが問題だと言われています。ひょっとしたら今後は、受給者証の発行の部分で深く関わってくるかもしれません。
特に「どういう支援が必要なのか?」という側面では、児童発達支援センターの役割が求められるのではないでしょうか。
これはあくまで私個人の意見なので、今後の見解や行政の資料からも検討しなければならないと思います。
2、児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・あり方について
●平成24年度の制度再編以降、児童発達支援・放課後等デイサービスのサービス利用者数は大きく増加しており、サービスの内容がさまざまに広がり、なかには補習塾的な機能や預かり中心の事業所もあるとの指摘がある。
こういう書き方をする背景には、放課後等デイサービスのあり方として「補習塾的な機能や預かり中心の事業所は望ましくないということが読み取れます。
サービスの内容がさまざまに広がること自体は悪い話ではありませんが、放課後等デイサービスの本来のあり方的にどうなのか?という疑念は残ります。
●一方で、女性の就業率の上昇にともない、発達支援を必要とする障害児の保護者の就労を支える役割を求められている側面もある。
●また、放課後等デイサービスについては、専修学校・各種学校に通う障害児は対象になっていない。
●これらの点についてどう考えるか? …など
ここから読み取れることは、「放課後等デイサービスにはそろそろ障害児の学童保育的な役割も担わせていいのではないか?」ということです。
学童保育的な役割を担わせるということは、逆に言うと『報酬単価の減額』あるいは『10名定員による運用の不要』と言えます。
今は新型コロナウイルスの影響もあるため、あまり大人数を集めるのは良くありませんが、おそらく預かり型をメインでやるのであれば15名定員や20名定員での運用も考えらえます。
そのかわり『発達支援』という部分については実質要求しない、という形になる可能性がありそうです。
3、インクルージョンの推進について
●児童発達支援・放課後等デイサービスの充実により、従来は障害と認識されずに育てづらさ、生きづらさを抱えていた児童が、新たに発達支援に繋がるようになった一方で、適切な支援を受けながら一般施策(保育所・放課後児童クラブ・放課後子ども教室など)を利用することが選択肢として検討しづらくなっているという指摘もある。
●こうした状況もふまえ、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進において、児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の役割についてどう考えるか? …など
今後は支給決定内容をある程度おさえ、保護者が就労しているのであれば週に何回かは学童に通ってもらう、ということも検討材料となりそうです。
学童に通っているお子さんだからこそ放課後等デイサービスも利用できる、という見方もあるのではないでしょうか。
あとは、保育園・幼稚園と児童発達支援との連携についても、これからの課題としてあります。
4、障害児通所支援の支給決定のあり方について
●障害児通所支援の支給決定は、障害児の心身の状態、当該障害児の介護をおこなうものの状況等を勘案して行うこととしており、障害児の心身の状態を把握する上で、5領域11項目の調査を行うこととしている。
●5領域11項目の調査では、食事や入浴等の身体介助の必要性(全介助・一部介助)および行動上の課題のみが把握され、発達支援の必要性の観点は含まれない。また、支給決定で決定するのは、サービスの種類とその利用日数であり、どのような発達支援を行うかは、保護者が選択した事業所に事実上委ねられている。
●こうしたことをふまえ、障害児通所支援の支給決定の在り方についてどう考えるか? …など
どのような発達支援を行うかは、保護者が選択した事業所に事実上委ねられています。
そのため「どのような発達支援を行うか?」ということが、支給決定のあり方へと絡んでくるかもしれません。
また、そこに児童発達支援センターの役割が追加されることも考えられます。
5、事業所指定のあり方について
●都道府県・指定都市・中核市は、児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請があったとき、必要量を満たす場合には指定を行わないことができる。
●一方で、同一都道府県等の中でも地域によって事業所の偏在が著しい場合や、総量としてはニーズが達成されているが対象者(医療的ケア児等)によっては受入事業所がないなど、事業所の配置に対し、都道府県等が適切に関与することが望まれる実情もある。
●しかしながら、自治体としての必要な事業所数の見込み方やどのような場合に行うことが適切か等について示しておらず、指定が効果的に実施されていないとの声がある。
●こうしたことをふまえ、事業所指定の在り方についてどう考えるか? …など
現時点では市区町村の意見書をベースとして、指定の有無を決めている自治体が多いように感じます。
なので今後は全国的に市区町村の意見書を必須とする流れになっていく可能性もあります。
まとめ
令和3年度法改正後の障害児通所支援のあり方については、今後もますます変化していくことを前提とし、早めに情報をキャッチしておくことがとても重要になります。
おそらく今後も3年から6年のスパンで変化していく、ということを理解しておきましょう。
3年後の法改正について解説するウェビナーを開催します!
小澤先生による今回の検討会についてを解説するウェビナーを開催します。
3年後の法改正の争点や予測がいち早くつかめる内容です。
皆様のご参加心よりお待ちしております。
ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
(1) 【令和3年法改正】2021年の報酬改定における事業所内相談支援加算に関わるQ&A
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における専門的支援加算に関わるQ&A
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定で創設された個別サポート加算I、個別サポート加算IIとは?
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点
小澤信朗先生のご紹介
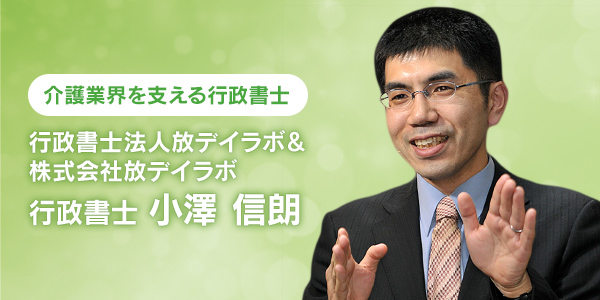
1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
>放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら
関連する記事
メールマガジンの登録
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
- アクセスランキング
- カテゴリ
- 最新の記事
-
-

看護の視点を取り入れたアセスメントで的確な療育につなげるために【株式会社イクシオ様】
-

「あなたは、そのままで良いんだよ」と伝えられる場所【株式会社ソノママ様】
-
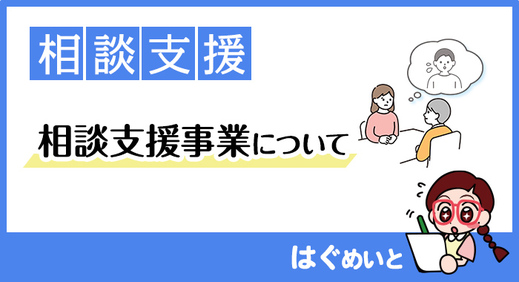
相談支援事業所について
-
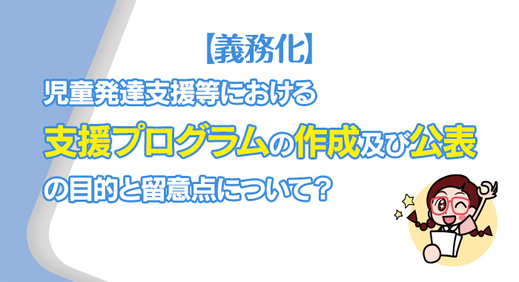
【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について
-

発達特性には早期療育と脳科学の視点を【特定非営利活動法人風の詩様】
-

5領域と一人ひとりにしっかりと関わる個別支援【医療法人社団ゆずか様】
-

地域のお困りごとを解決するために事業展開
-

会社も利用者も地域に根付いていく【株式会社ネオハル様】
-

事業所と保護者の想いを繋ぐ相談支援専門員
-

「子どもを人間として見る」学問の視点に立った療育【一般社団法人かりなぽーと様】
-